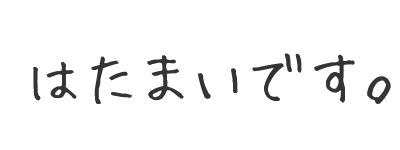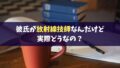診療放射線技師とは
こんにちは。
放射線技師のはたまいです!
今回は、診療放射線技師の仕事ってどんな仕事なのかを説明させてもらいます!

僕が高校生の頃は
放射線技師は「息を大きく吸って~」の印象しかありませんでした(;^ω^)
この記事を読んでいただければ
ざっくりではありますが放射線技師の仕事は何をするのかが分かっていただけると思います!
それでは参りましょう!
放射線技師について
最初に、ざっくり診療放射線技師について説明していこうと思います。
診療放射線技師とは
病院やクリニックにおいて医師の指示のもとで放射線を用いた検査や画像診断、治療に携わる医療技術職です。
注意点は、診療放射線技師だけでは検査することができず、医師の指示がないと撮影できないこと
放射線の取り扱いには特別な注意が必要なため
日本で医師と歯科医師以外で人体に放射線を照射することが認められているのは診療放射線技師のみです。
放射線を用いた検査はもっぱら診療放射線技師が行っています。
診療放射線技師が携わる業務は以下の通りです。
- 一般X線撮影(レントゲン)
- 乳房X線撮影(マンモグラフィ)
- 透視検査
- CT
- MRI
- 骨密度検査
- 超音波検査
- 放射線治療
- 核医学検査
名前を聞いたものもあれば、聞いたことがないものもあるのではないでしょうか(/・ω・)/
今回はこちらを手短に、ご紹介させていただきます!
放射線技師の業務
一般X線撮影(レントゲン)
皆さん一度は経験があるのではないでしょうか
「大きく息を吸って、止めてください」
と言われたあとに胸の写真を撮影されたこと(‘ω’)
それがレントゲンです。
レントゲン検査は、被ばく量が少なく、X線を使って体の中を写真のように映し出す検査です。
特に、骨や肺の様子を調べるのに使われます。
例えば、骨が折れていないか確認したり、肺炎などの病気がないかを調べたりします。
検査を受けるときは、体の一部にX線を当てて、反対側にある機械でX線の通り方を記録します。
骨はX線を通しにくいので白く映り、肺など空気の多い部分は黒っぽく写ります。


乳房X線撮影(マンモグラフィ)
マンモグラフィは、乳房専用のX線検査で、乳がんの早期発見に効果的な検査です。
検査自体は、一般撮影と原理は同じですが
専用の装置で乳房を薄く挟んで圧迫し、上下・左右からX線撮影を行います。
乳腺やしこり、石灰化(小さなカルシウムの沈着)などを写し出し
触診ではわかりにくい初期の乳がんを見つけることができます。
現在は、病院の方針で男性技師が検査を担当することもありますが、
セクシュアル・ハラスメントの観点より女性技師が担当することがほとんどです。
透視検査
透視検査は、X線を使って体の中の動きをリアルタイムで観察する検査です。
レントゲンが静止画のような検査であるのに対し、透視は動画のように動きを確認できるのが特徴で
造影剤(体の中を映りやすくする薬)を使って、臓器や血管、関節などの状態を詳しく調べることができます。
胃透視(上部消化管造影):バリウムを飲んで食道や胃、十二指腸の形や動きを調べる
嚥下造影検査(VF):食べ物や飲み物を飲み込む様子を観察し、誤嚥や嚥下障害の有無を評価する
血管造影検査:カテーテルを血管に挿入し、造影剤を流して血管の狭窄や閉塞、出血の部位を調べる
関節造影や整復時の透視:関節内に造影剤を注入して靱帯や関節の状態を調べたり、骨折部位の整復の確認
CT
CT(Computed Tomography)検査は、X線を使って身体の内部を断面画像として撮影する検査です。
レントゲン写真が一方向から撮る「平面画像」であるのに対し
CTは体を輪切りにしたような「断面画像」を多数撮影し
それをコンピュータで再構成することで、より立体的で詳細な情報が得られます。
検査では、ドーナツ状の機械の中にベッドごと入って
数分間静かに横になるだけで短時間で広い範囲の画像を撮影できます。
主に、頭部外傷や脳出血、肺炎や腫瘍、腹部の炎症や出血の評価などに使われる検査です。
被ばくを伴う検査ではありますが、医療現場では必要性を考慮して、安全に実施されます。
救急医療や精密検査において、なくてはならない重要な画像診断法です。
また、最近のCTでは、性能が向上していき、検査時の被ばくが従来よりも低減してきています。

CTでは好きな方向から骨の状態を見ることができ
レントゲンよりも骨折の部分が見やすいこともあります。
MRI検査
MRI(Magnetic Resonance Imaging)検査は、磁場を使って体の内部を画像化する検査です。
X線を使用するCTとは異なり、放射線による被ばくがないのが特徴です。
体内の水分や組織に含まれる水素原子の動きを利用して
脳や脊髄、関節、内臓などの詳細な断面画像を得ることができます。
検査中は筒状の装置に横になって入り、強い磁場の中で数分から数十分ほど静止した状態で撮影を行います。
撮影中は大きな音がするのが特徴的です。
特に脳の病気(脳腫瘍・脳梗塞など)や椎間板ヘルニア、靭帯損傷、子宮や前立腺の病変評価などに使われます。
金属を体内に入れている方(例えば心臓ペースメーカー)は
MRI検査ができない可能性があるため注意が必要です。
骨密度検査
骨密度検査は、骨の強さを数値化して、骨粗鬆症や骨折リスクを早期に見つけるための検査です。
一般的なのは、 DXA(デキサ)法 と呼ばれる方法で
腰椎や大腿骨などにごく少量のX線を当て、骨に含まれるカルシウム量を測定します。
骨密度検査は、見た目は地味な検査に見えますが
患者様の生活習慣の改善や治療方法に大きく関わってくる検査です(;’∀’)
超音波検査
超音波検査は、放射線は使わず、超音波を使います。
こちらの検査は、放射線技師だけでなく臨床検査技師、医師が担当していることもあります。
こちらの検査は、放射線による被ばくがないまま検査ができるという利点があります。
他の検査では分からなかった、心臓の機能や肝臓・膵臓の状態などを知ることができます。
しかし、超音波検査は、検査を担当する人の技術に左右されやすく
検査を担当した人が病気を見逃してしまうと、病気の発見が遅れてしまう可能性もあります。
そのため、超音波検査はすべての検査においてトップクラスに技術が求められる検査です。
放射線治療
放射線治療とは、診療放射線技師が医者と共に患者の癌を治療することができる唯一の業務です。
がん細胞が正常細胞に比べ放射線に弱いことを利用し、病巣に放射線を照射することでがんの治療を行います。
・病変が限局している場合、がんの存在する臓器の形や機能を残したまま治すことが出来ること。
・全身への負担が少なく、高齢者や体力のない患者さんでも治療可能
治療の目的は、完治を目指す場合と苦痛を緩和する場合の2つに分かれます。
また、手術や薬物療法と併用することもあります。
しかし、癌だけに照準を合わせることが難しいため
癌以外の正常な細胞も一緒に死滅させてしまうため副作用が出てしまいます。
また、対象患者様は、全員癌を患っている方になるため、精神面の配慮には注意が必要です。
核医学検査
核医学検査とは
特定の臓器や組織に集まりやすい性質を持った放射性医薬品(放射性同位元素)を使って
そこから放出される放射線を画像化することにより体内の様子を調べる検査です。
レントゲンやCTは、撮影の際に被曝しますが
核医学検査は、ほかの検査と違い、薬剤が体の外に排出されるまで被曝し続ける特徴があります。
そのため、放射線治療と同様に、患者さんへの精神面へのケアが必要な場面もあります。
最後に
ここまで読んでいただきありがとうございました!
診療放射線技師の実際の業務を知って、驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
将来、診療放射線技師になってみたい方や放射線技師の仕事について知りたい方の
参考になっていただければ幸いです(‘ω’)